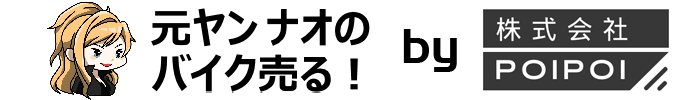バイクのタイヤはエンジンやブレーキと同じくらい重要な部品とも言えます。
いくらパワーがあるエンジンやしっかり止まれるブレーキがあっても、それを路面に伝えているのはタイヤとなるわけですからね。
そのため、ある意味タイヤによってバイクの性能が最大限使えるとも言えるのです。
そんな重要な部品でもあるタイヤは、様々なメーカーからたくさんの種類が販売されています。
でも、「ぶっちゃけタイヤなんてどれも一緒じゃないの?」と思う人も少なくないと思います。
タイヤなんてパターンはいろいろありますが、大きく形状が違うわけでもありませんし、街中を流して走ってるのであればほとんど気になることもないでしょう。
しかしタイヤについて詳しく調べてみると、構造や種類、サイズなど、たくさんの違いがあるのも事実です。
これらをすべて把握して自分のバイクに適したタイヤを選べるのがベストですが、なかなかピンと来ない人も多いと思います。
そこで本記事では、バイクのタイヤについての構造や種類などの基本的な知識についてをご紹介ます。
また、後半には選んでおけば間違いないおすすめのタイヤについてご紹介していきますので、ぜひ参考にしてみてください!
バイクのタイヤの種類は3種類ある

まずはタイヤの種類についてご紹介していきます。タイヤの種類は、次の3種類に分けることができます。
- チューブレスタイヤ
- チューブ入りタイヤ
- ノーパンクタイヤ
チューブレスタイヤ
タイヤ内にチューブが存在せず、代わりにタイヤ内部に貼り付けられた「インナーライナー」と呼ばれる部分が、ホイールのリム部分に密着し、空気が逃げないようになっています。
チューブレスタイヤ最大の特徴は、パンクしにくいことです。
例えば走行中に釘を踏んだ場合、チューブ入りタイヤだと内部のチューブから簡単に空気が抜けてしまいます。
しかしチューブレスタイヤは釘が刺さっても、そのままの状態である程度走行が続けられるのです。
また、タイヤ内の空気がタイヤ全体に接しているため、走行風で効率よく冷却できるのです。
他にもタイヤ交換の際にチューブの取り外しがしやすかったり、交換時のメンテナンスが必要ありませんので、手間がかかりません。
反対にデメリットとしては、チューブレスタイヤはバンクをしても空気圧が抜けにくいため、目視で確認ができません。そのため定期的にタイヤ全体を確認する必要があるのです。
チューブ入りタイヤ
チューブを膨らませてタイヤを内部から押し広げるチューブ入りタイヤは、衝撃に強くパンクしにくい特徴があります。
また、チューブ単体が膨らんで形状を維持しているため、ホイールが変形してもタイヤの形状を維持し続けることができます。
そのためチューブ入りタイヤはオフロードバイクやクラシックバイクに多いとも言えますね。
ただしデメリットは、釘などが刺さると簡単に空気が抜けてしまうこと。
また、パンクの修理をするための取り出し・はめ込みも難しく、慣れない人がタイヤを組めば、チューブを損傷させてしまうなんてことも起こります。
ノーパンクタイヤ
自転車の世界では有名かもしれませんが、実はバイクのタイヤにもノーパンクタイヤが存在します。
タイヤ内部に特殊素材ポリマーが吹き付けられており、パンクした穴を瞬時に防いでくれます。
残念ながら日本のタイヤメーカーではまだ販売されていませんが、理論上は特殊素材ポリマーを内側に吹き付けられればどのようなチューブレスタイヤにも利用することができるため、今後開発が期待される技術でもあるのです。
バイクのタイヤの構造は2種類に分られる

続いてバイクのタイヤの構造について見ていきましょう。
バイクのタイヤは基本的に路面をとらえるゴム「トレッド」の部分と、強度を保つ「カーカス」と呼ばれる部分に分けられます。
カーカスはスチールや合成樹脂といった素材が束ねられたもので、何層にも重ねることでタイヤの原型を作っています。人間で言うと骨の部分とも言えますね。
そして束の重ね方によって2種類に分けられます。
- ラジアルタイヤ
- バイアスタイヤ
この2種類の構造はそれぞれ異なる特徴を持っており、一概にどちらが優れているとは言い切れません。バイクのキャラクターによって適した構造のタイヤが使われるのです。
それぞれの特徴を見ていきましょう。
ラジアルタイヤ
トレッド部分と直角に強度を持たせるようにワイヤーが配置されており、タイヤの外周方向に対し、強度を持たせるために補強材も巻かれています。
また、カーカスとベルトが明確に分けられているため、タイヤの開発がしやすいメリットもあります。
タイヤ自体の剛性も高くできるため、スポーツタイプのタイヤやレージングタイヤもラジアル構造が採用されています。
反面、乗り心地はバイアスタイヤに劣るため、ツアラー系のバイクには向いていないとも考えられます。
さらに製造コストも高いため、物によってはかなり高価なタイヤとなることもあります。
バイアスタイヤ
バイアスタイヤは、ワイヤーを層のように交互に巻くことで強度を増している構造です。
もともとタイヤが開発された時の構造で、古くから用いられている構造とも言えます。
タイヤ表面の強度は非常に高くなっていますが、ラジアルタイヤと比べて柔軟性が高く乗り心地自体は良いとされています。
一方でタイヤ全体の耐久面はラジアルタイヤに比べて劣りますので、剛性を高めようとすればタイヤ自体をゴツくしなければいけません。
しかしタイヤ自体の製造コストはラジアルタイヤに比べて低いため、比較的安く手に入れることができます。
原付やスクーターなどの車体や通勤・通学をメインに乗るのであれば最適なタイヤですね。
バイクのタイヤの原型を作っている素材も大きく2種類に分けられる

ここまでタイヤの構造や種類についてご紹介しましたが、他にも知っておきたいこととして、タイヤの原型を作っている素材についてがあります。
タイヤの素材は、大きく分けると次のようになります。
- スチール主体
- 合成樹脂主体
簡単に言うと「金属製」か「合成樹脂製」かの違いとなります。
スチール主体
スチールは金属ですので、タイヤが温まりやすい特徴があります。
タイヤは基本的に作動温度があり、適温に達していないタイヤは本来の性能を発揮させることができません。
街乗りタイヤの作動範囲は低く設定されており、真冬でもある程度グリップさせられるようにできています。
しかし走行風によってタイヤ表面が冷えてしまうことも少なくありませんので、タイヤの温度を維持するのは非常に難しくなるのです。
そんな時にタイヤをしっかり温めるポイントが「芯の部分」。
スチールは熱伝導率が良いため、タイヤの芯の部分を温めるのに適しているのです。
また、スチールは変形すればするほど分子が擦れあって熱を放出するため、発熱しやすいとも考えられます。
さらにスチールは強度も高く剛性を高くすることができますので、大きなバイクや車重が重いタイヤにとっても非常に相性が良いのです。
ただし内部の温度を上昇させやすいと言うことは、内部の空気が膨張しやすいとも考えられますので、あえて窒素を入れて膨張を抑える対策もされています。
合成樹脂主体
スチールの代わりに「ケブラー」「アラミド繊維」「ポリアラミド繊維」などの合成樹脂を使用するタイヤも存在します。
金属のスチールと比べて軽量という特徴がありますので、コーナーでの安定性や高速道路やスポーツ走行向きのタイヤに向いている素材と言えるでしょう。
タイヤなどの回転体は軽ければ軽いほど運動性が良いため、高速回転するシチュエーションにもしっかり対応できるんですよね。
デメリットとしては熱伝導率が悪いため、タイヤが温まりにくいこと。
ただし最近のタイヤはトレッド表面が柔らかいものが多く採用されており、表面からタイヤを発熱させますので、ネガな部分は徐々に消えつつあります。
さらにスチールと合成樹脂を併用している新素材のタイヤも開発されてきました。
バイクのタイヤに書いてある表記の見方

バイクは車種やジャンルによって使用するタイヤのサイズが違いますので、そのバイクに適したサイズや規格のものを選ぶ必要もあるのです。
タイヤに書かれている基本的な表記について見てみると、次のように分けられます。
- タイヤサイズ等
- 速度記号
- ロードインデックス(荷重指数)
- タイヤの空気圧
これらはタイヤのサイド部分に記されています。国内で統一された記号でもあるため、メーカーが変わっても読み方は変わりません。
1.タイヤサイズ等

タイヤサイズについての情報は、次の数字に表されています。
- タイヤ幅・・・タイヤを前から見たときに一番太い幅。この場合は160mm
- 扁平率・・・タイヤがどれくらい平かどうかの指標。数値が低いほどタイヤが平らになる
- ラジアル構造表記・・・ラジアルタイヤは「R」「ZR」の記号が付く※ZRは最高速度が270km/hを超えるタイヤ
- リム径・・・ホイールサイズ(インチ)
- モーターサイクルタイヤ表記・・・4輪タイヤとの混同を防ぐために表記
基本的には車両の用途やサイズによって指定されていますので、取扱説明書などを見て指定のサイズのものを選べばOKです。
2.速度記号
規定の使用条件で走ったときに、そのタイヤが耐えられる最高速度を表します。
単位は「km/h」で表され、速度によってアルファベットが割り当てられます。
ちなみに100km/hの速度記号は「J」、200km/hだと「U」となるように、速度が高くなればなるほどアルファベットの記号も進んでいきます。
もしバイクの最高速度よりも低い速度記号のタイヤだと、高速走行中にタイヤがよじれたりバーストする危険がありますので、適切な記号のものを使用しましょう。
3.ロードインデックス(荷重指数)
規定の使用条件を速度記号で走ったときにタイヤが耐えられる最大荷重を表します。
単位の方は「kg」で、この力のことを「負荷能力」と呼ばれます。ちなみに耐荷重100kgのタイヤの荷重指数は28となっているように、あらかじめ決められた数値となります。
車両の重量やジャンルによって必要な荷重指数が分かれており、指定の荷重を下回るタイヤを使用すると、段差の衝撃を受けたときや急ブレーキをかけたときにバーストしてしまう可能性もあります。
そのため適切な指数のタイヤを選ぶようにしましょう。
4.タイヤの空気圧
タイヤの空気圧は、そのバイクに書かれている規定値を入れましょう。
大体の場合はそのバイクのスイングアームステッカーで貼られています。また、タイヤによってはサイド部分に書かれていることもあります。
空気圧は「高め」や「低め」と言ったように調整することで、タイヤのキャラクターを変化させることもできます。
ただしやりすぎると反対にグリップが低下したり、バイクの操作性が悪くなる可能性もありますので、基本は規定値にしておくことをおすすめします。
バイクのハイグリップタイヤはノーマルとどう違うの?

サーキットを走る時や、峠を攻める時などにおすすめのタイヤがハイグリップタイヤです。
ハイグリップタイヤはラジアルタイヤのコンパウンドが柔らかく、グリップが高くなっています。
スポーツ走行向けのタイヤですので、「スポーツタイヤ」とも呼ばれています。
ハイグリップタイヤであれば路面をしっかり掴んでくれるため、急カーブでも高いスピードで走ることができます。
また、ブレーキも強力にかけられるため、短い制動力が得られるのです。さらにハイグリップタイヤはタイヤパターンもカッコよく、スポーティな印象もあります。
一方でハイグリップタイヤは柔らかい素材のゴムを使用しているため、寿命が短い特徴があります。
通常のタイヤと比べて半分以下のライフのタイヤも少なくありません。もちろん価格も高いので、サーキット走行のとき限定に使うなど、通常のタイヤと使い分ける方が良いかもしれませんね。
ツーリングにおすすめのタイヤ

バイクのタイヤに関しての基本的な知識が身についたところで、いよいよおすすめのタイヤをご紹介していきます。
まずはツーリングなど、長距離走行に向いているおすすめのタイヤを見ていきましょう。
【ブリヂストン】BATTLAX HYPER SPORT S22

スポーツタイヤの中では定番中の定番タイヤで、街乗りからツーリングまで幅広く対応しています。
ツーリング中は一定速度域での走行が多く、走行風も当たるため、使用温度域が低くなりがちです。
S22はスポーツタイヤでありながら低温から中温域のグリップが安定しており、ストリート領域で最大のグリップを引き出せるようになっています。
タイヤが冷えている状態の走り出しや高速道路など走行風が当たるシチュエーションでも安心して楽しむことができるでしょう。
また、S22はサイド部分のパターンも増えており、撥水性も非常に高くなっています。
特にバンクした際の溝の多さはスポーツタイヤの中でもトップクラスですので、急な雨でも安心して走行することができるでしょう。
タイヤ全体が比較的高い剛性となっていますので、もちろんワインディング走行でもキビキビと走ることができます。
さらにトレッドのセンター部分は、グリップが高い素材を使用しているため、大きく加速してもスピンすることなく路面を蹴り出してくれるでしょう。
反対にピレリタイヤなどの低圧タイヤに乗り慣れていると、接地感が少なく不安になることもあるかもしれませんが、入力すれば入力しただけ反応するタイヤですので、慣れれば反対に安心して楽しむことができるでしょう。
【ミシュラン】ROAD 5

グリップ力が高いことで有名なミシュランタイヤは、タイヤライフが短く、ツーリングに向いているタイヤはあまり多くはないんですよね。
しかしROAD 5は比較的タイヤライフが長く、快適性とハンドリングの素直さがという面で非常に高評価を得ています。
コントロールしやすいタイヤは、ワインディングロードでも素直に曲がってくれるため、長距離走行でも疲れることはありません。
タイヤライフはシチュエーションによっても異なるものの、ツーリングなら2万キロ近く持つロングライフを実現。
5分山ぐらいからハンドリングや衝撃吸収性は落ちてくるものの、満遍なく下がってくるため、しっかり最後まで使い切ることもできます。
また、5,000キロ走行でも全モデルのROAD 4と同等のウエット性能も持っており、信頼できるタイヤであると評価できます。
持ち前の高いグリップ力を生かして峠ではちょっとハイペースに走ってもゆったり走っても良しの万能タイヤですね。
【ピレリ】エンジェルGT

タイヤメーカーの中では唯一指定空気圧が低い「低圧タイヤ」を開発・販売しているピレリのタイヤ。
剛性が低くしっかり路面に接地することによってライダーが安心して乗れるような設計となっています。
しかしエンジェルGTは、あえて剛性を上げてタイヤの形状をしっかり確保するような構造となっています。繊維の割合はエンジェルSTに比べ約32%も増加しています。
また、タイヤのエッジ部分の剛性を上げることで、サイド部分全体のグリップ力、耐摩耗性能が向上しているため、長距離移動での摩耗性が大きく向上しています。
もちろんトレッド部分の撥水効果も高めるために溝も大きく削られています。
ピレリタイヤはもともとコンパウンドは柔らかめの傾向でしたので、雨天時のグリップに定評がありましたが、パターンが多くなったおかげでさらに安定感をもたらしてくれるタイヤとなりました。
BMWのスポーツツアラーにも採用されているほど、ビッグバイクとも相性が良いため、ツアラーバイクやアドベンチャーバイクを乗っているのであれば、選んでおけばまず間違いのないタイヤとも言えますね。
【ブリヂストン】T30EVO

ハイグリップタイヤの中では絶対的なグリップは劣るものの、軽快なハンドリングやウエット性能向上に定評のあるタイヤとなります。
ツーリングに求められるドライ&ウエットでの高い走行性能を両立しているのはもちろんのこと、転がり抵抗も少ないため、直進安定性も非常に優れています。ロングツーリングに最適なタイヤとも言えますね。
グリップ性能全域で向上しており、ウエット走行でも安心してスロットルを開けられるのは非常に安心です。大きな荷重をかけてもタイヤ自体の変形量が少ないため、ひらひらと切り返しもできます。
あまりコーナーを攻めない人であれば、最初に試してみる価値のあるツーリングタイヤですね。
サーキット走行におすすめのタイヤ
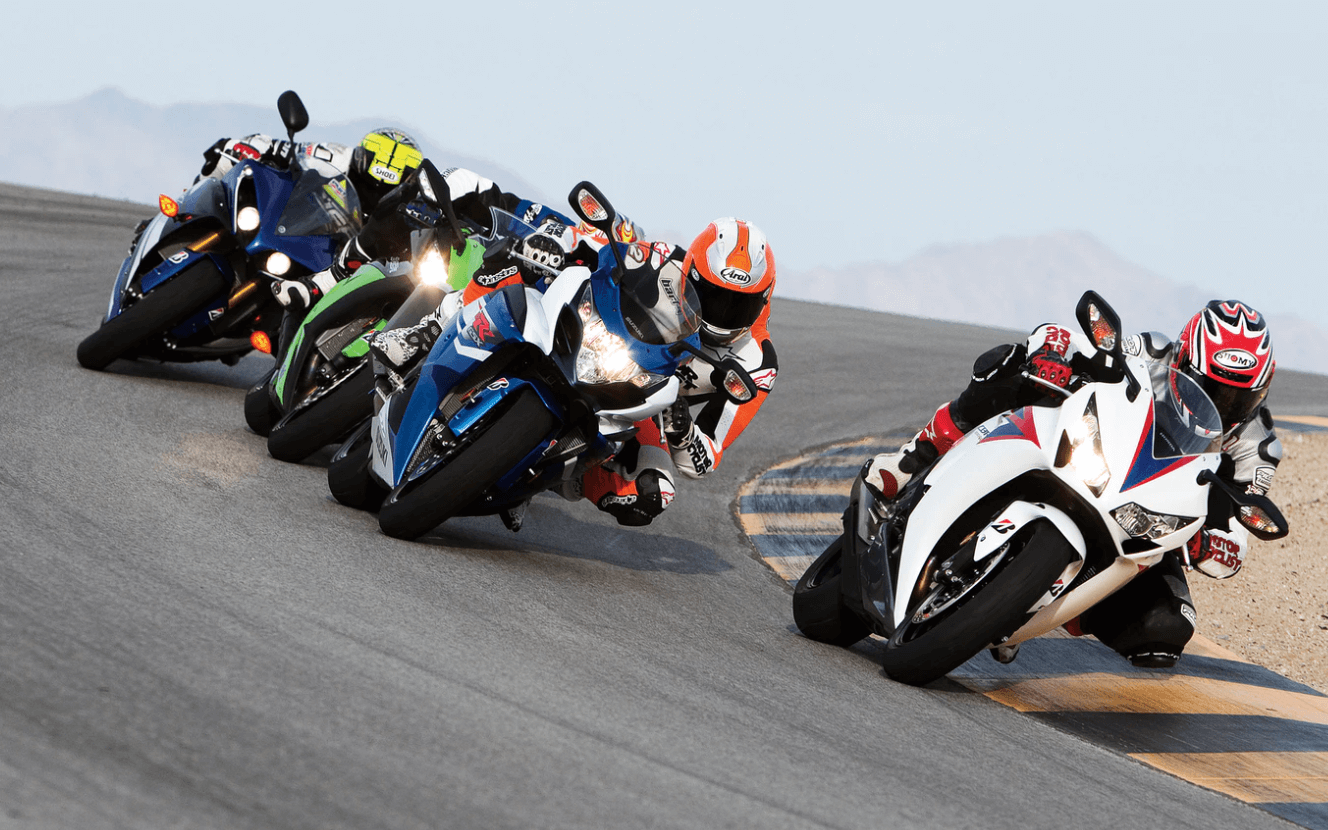
サーキットを走る時は、グリップやコントロール性が高いタイヤが非常に重要。
また、ブレーキングや加速、コーナリングGなど常に大きな負荷がかかるため、サーキット走行でも耐えられるハイグリップタイヤを選ぶようにしましょう。
大きな荷重がかかるサーキット走行では、各タイヤメーカーによって違いも感じ取りやすく、タイヤ作り方の考え方も知ることができるでしょう。
【ブリヂストン】BATTLAX R11

サーキット走行用に開発されたタイヤで、購入するには書面による申込書を提出しなければいけないサーキット専用タイヤです。
非常に高いグリップで、タイヤウォーマーなどを使ってしっかり作動温度まで高めてあげなければ本来の性能が発揮できません。
しかし一度グリップし始めれば強烈に路面に食いつくレーシングスポーツタイヤです。
ベルト構造はブリヂストン独自の「V-MS・BELT」を採用しており、均一にグリップするような剛性を確保。
さらにリアタイヤは駆動力がかかった際に高い横力が発生するため、横滑りが抑えられる構造をしています。
コーナー出口からしっかりスロットルを開けられるようになったため、前型のR10と比べてラップタイムも約1秒以上速くなったというデータもあります。
ロードレースのST600クラスの指定タイヤにもなっているため、スペック的には申し分なく、使いこなせばバイクの性能を100%引き出すことができるでしょう。
【ピレリ】ディアブロ スーパーコルサSP

サーキット走行はもちろんのこと、峠などの公道でも高いグリップを誇るピレリの最強スポーツタイヤがディアブロ スーパーコルサSPとなります。
スーパーコルサという名前は、ピレリが販売するハイエンドスポーツタイヤのブランド名で、低温からでも圧倒的なグリップ感があります。
また、ピレリタイヤ自体が低圧タイヤですので、ライダーが安心できる高い接地感も合わさり、スポーツ走行に慣れていない人でも思い切ったライディングができるのです。
さらにスーパーコルサは、耐久性やグリップ力もトップクラスですので、ヨーロッパを中心に開催されるWSS(スーパーバイク世界選手権)の指定タイヤにもなっています。
市販のスーパースポーツバイクであるドカティパニガーレやホンダCBR1000RRの標準タイヤにも採用されてもいますので、非常に信頼性が高いタイヤとも言えるでしょう。
一度使うと「他メーカーのタイヤは使えない」という人もいるくらいですので、サーキットを速く走りたい人はぜひ使ってみてはいかがでしょうか。
【ダンロップ】SPORTMAX Q4

UKダンロップがスリックタイヤをベースに開発したタイヤで、公道走行も可能なハイパースポーツタイヤとなっています。
一番の特徴は、レース用スリックタイヤと同等のフルカーボン・コンパウントや、ジョイントレス・トレッド構造の採用によりタイヤ自体の剛性が非常に高くなっています。
これにより、リアタイヤのコーナリング時の接地面積が非常に高くなり、公道でも高い安全性を実現しているのです。
コーナリング中は張り付くようなグリップ力が大きな特徴で、最大バンク角62°の記録もあります。
流石に路面温度がマイナスとなる真冬では使用を控えた方がいいですが、しっかり走ってタイヤを揉めば、ある程度のグリップは保証されます。
タイヤをグリグリと押しつけて走る乗り方が要求されるため、技量が必要かもしれませんが、その分乗りこなした時の旋回力はかなりもの。
ライダーを育ててくれるタイヤでもあるため、ライテクを磨きたい人であれば使ってみる価値は十分にあります。
【メッツラー】Sportec M7RR

メッツラーのハイグリップタイヤは、マン島TTレースなどの公道レースでの需要も高く、ヨーロッパでは高い評価のタイヤが非常に多くなっています。
特にM7RRは「一般道性能最高」を掲げて開発されたタイヤで、様々な状況下で性能を発揮できるように設計されています。
一般道では、舗装された路面の割れや荒れ、凸凹や路面上のほこり、白線など、様々な悪条件が待ち受けています。
また、気温や天候によって毎回決まったコンディションもありませんので、タイヤからすればかなり過酷なコンディションでもあります。
そんな路面状況の中時速200km/h以上で走るマン島TTレースで磨かれたのがM7RRとなるわけです。
タイヤ内部構造のカーカスは走行時に遠心力でタイヤが膨張しないよう、ある程度強度が保たれていることに加え、路面の凹凸もしなやかに受け止められるような柔軟性も残しています。
また、タイヤパターンを見てみると、直進時にタイヤが地面に接する部分にはスリックタイヤのようにパターンを少なくし、バンクし始めた直後に深い溝が設けられています。
さらに深くバンクしたときには、あえて浅い溝とすることで、接地部分の変形を抑えられるようにもなっています。
リアタイヤのコンパウンドもセンター部分に硬めの素材を使用することで、ロングライフも実現しています。
コスパ重視でオールマイティー:選んでおいて間違いないおすすめタイヤ
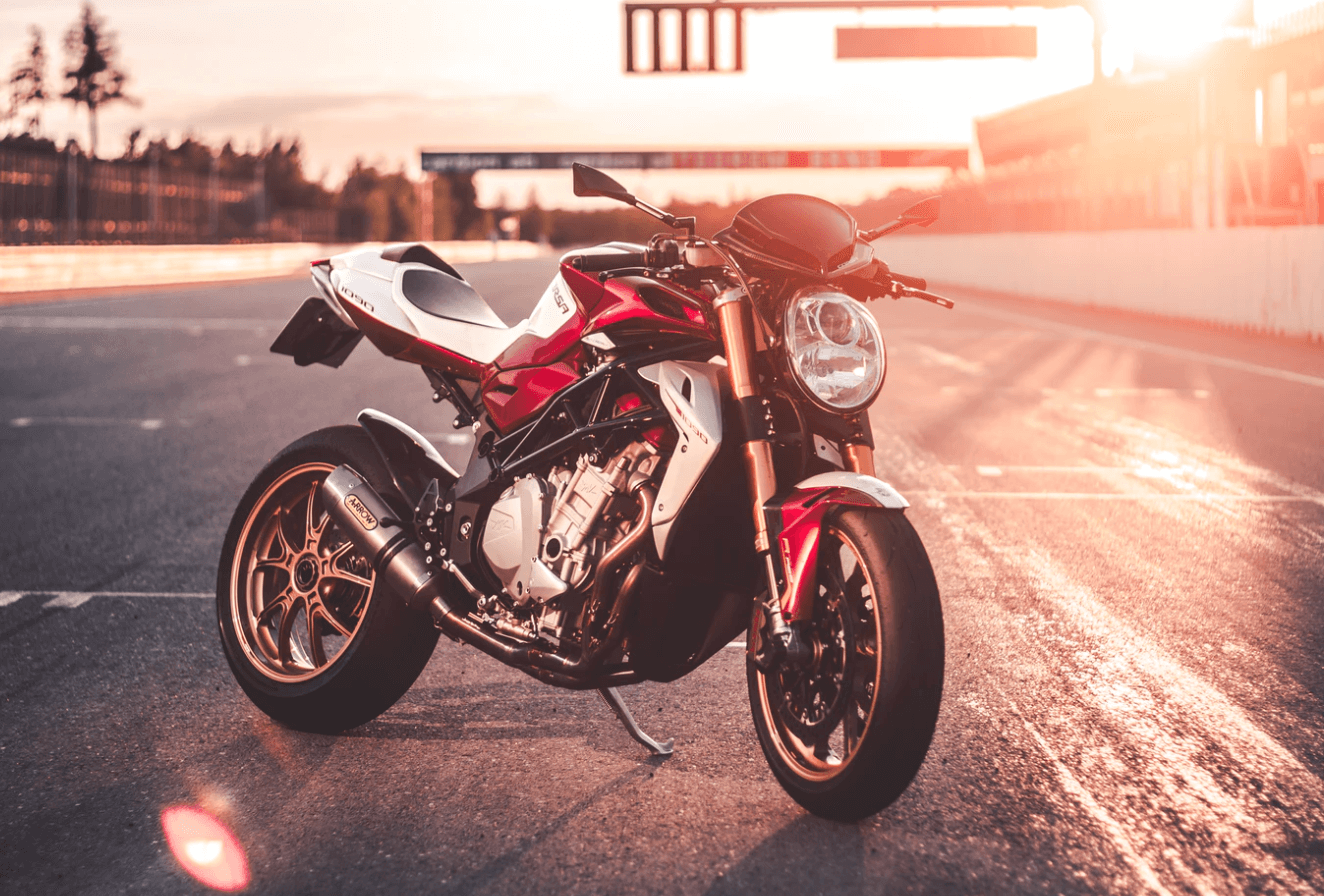
最後に「街乗りやツーリングもするし、たまにサーキットも走ってみたい!でもなるべくお金もかけたくない」そんな良いとこ取りをしたい人におすすめのタイヤをご紹介していきます。
比較的値段もリーズナブルでグリップもそこそこ、おまけにツーリングなど長距離移動もできるオールマイティーなタイヤとなります。
突出した性能はありませんが、どうしてもバイクのタイヤ選びに迷ったら、まずはこの中から選ぶと良いかもしれません。
【ダンロップ】α-14

国内公道タイヤで最も有名なスポーツタイヤで、どのようなバイクにも相性抜群。
センター部分は高い剛性を維持しているため、スーパースポーツからネイキッドまで幅広いジャンルのバイクで使用されています。
パターンデザインも「α」シリーズ伝統の「シェブロンパターン」が採用されており、非常にレーシーなイメージです。
フロントタイヤの断面形状はセンターを頂点にやや尖った形をしているため、大きくバンクした時にしっかり地面に接地するような設計となっています。
リアタイヤは重量があるバイクでも腰砕け感が起こらないよう。剛性自体を高くしています。これによってしなやかさと強さの両立とが実現しています。
ハイグリップタイヤの分類にも入るかもしれませんが、どんなバイクに装着させても間違いのないタイヤですので、あえてこちらでご紹介させていただきました。
【ブリヂストン】BT016 PRO

街乗りからちょっとしたスポーツ走行に向いているオールラウンドなタイヤです。
開発時は「運動性を重視しながらウエット性能や耐摩耗性にも配慮した公道タイヤ」という位置付けで、グリップ力は決して高いとは言い切れません。
ただし排水性が非常に高いパターンを採用しており、日常生活を行う上で必要な操作性や安定感を重視して作られているため、ストリートユーザーにはピッタリなタイヤとも言えるのです。
リアタイヤには世界唯一の5分割トレッドが採用されており、ストリートタイヤの先駆けとなっているタイヤでもあります。
スポーツ走行でゴリゴリに攻めると偏摩耗してしまう難点がありますが、普通に使っている分には特にネガな部分はありません。
【ミシュラン】パイロットロード4

ストリートファイターにとって必要な部分は雨天時の排水性ではないでしょうか?
ツーリング中の予期せぬ雨も考えられますからね。そうなるとおすすめなのがミシュランのパイロットロード4です。
溝が深いタイヤは排水性が高いのはもちろん、トレッド部分も非常に柔らかく、ライダーにとっては安心して扱えるタイヤとなっています。
そのためストリートユーザーに対しては非常に心強いタイヤとなるはず。
また、安心感があるタイヤは余裕を持ったバンク角まで倒すことができますので、自然とバイクの扱いにも慣れてきます。
ハイグリップタイヤは強力なグリップ力が故にタイヤを使い切る技術が要求されますが、パイロットロード4は良い意味でクセがありませんので、バイク基本を学ぶには最適なタイヤとも言えるでしょう。
【メッツラー】SPORTEC M5

「公道からサーキットまで自走し、サーキットでそのまま膝すりができるタイヤ」とのコンセプトのもと開発されたタイヤとなっています。
ただし、どちらかと言えば街乗りに重きを置かれて開発されたタイヤで、長寿命とグリップのバランスが優れたタイヤとなっています。
また、リアタイヤは5つにグリップ配分されており、街乗りであっても均等に摩耗していきます。
反対にサーキットを攻めるとサイド部分が大きく減ってしまいますので、山なりのタイヤになりがちでもあるんですけどね。
他にもタイヤの暖まりも良く、冬場のグリップ感も他のスポーツタイヤと比べて高めの傾向です。
ある程度攻め込んでもタイヤの減り方はさらっとしているため、絶対的なグリップは少ないものの、コントローラブルなタイヤとも考えられます。操作性を求めているのであれば、選んで間違いないタイヤですね。
まとめ
バイクの足元を支える重要な部品でもあるタイヤは、バイクの性能をきちんと路面に伝えるだけでなく、ライダーをやる気にさせるなども要素も必要になります。
バイクのタイヤ選びで重要なことをまとめると、以下の2つが考えられます。
- ツーリングやサーキット走行など、使用目的をきちんと決める
- 冬場やウエット時の性能も確認する
バイクのタイヤはメーカーも様々で、性能も千差万別。
そんな中でいきなり自分のバイクにあったタイヤを選ぶのも無理がありますが、今回ご紹介したタイヤはどれも信頼できるものばかりですので、この中からお気に入りのタイヤをぜひ見つけてみてください!